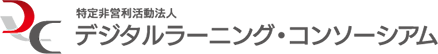- HOME
- デジタルラーニング関連情報
- アーカイブ
- ◆連載「海外のeラーニング事情」(2003年~2014年)
- 第30回 上流から見たeラーニング 12 ビジネスの成長と社員の成長につながる「ソーシャル・ラーニング」後編
第30回 上流から見たeラーニング 12 ビジネスの成長と社員の成長につながる「ソーシャル・ラーニング」後編
2010/03/23
Twitterはビジネスにつながるのか?後編
前回はTwitterに焦点をあて、サウスウェスト航空、デルにおける取り組み事例をご紹介した。今回はより広くソーシャル・ラーニングに取り組んでいる企業の事例と、そこから見えてくるメリットや課題について考察する。
1.イノベーション
企業の将来的成長にはイノベーションは欠かせないと分かっていても、不況のときにイノベーションにつながるための基礎研究に時間と投資をすることは難しい。大手電力会社のPacific Gas & Electric はWeb上にコンテストの場を提供し、社外から製品アイデアを募った結果、イノベーションを創出し乗り切ってきた企業の一つである。今ではPG&E社のイノベーションの50%以上は社外からだという。PG&E社のように、社内と社外を結びつけた「ソーシャル・ラーニング」を通してイノベーションを創出している企業は多い。
デル社:社内からは生まれなかったヒット商品
社外からのアイデアが商品化
コンピューター会社デルのIdeaStormは、カスタマーや一般から製品アイデアを出してもらうというコミュニティー・サイトである。カスタマーも社員も使いやすいようにということを第一として、クラウドコンピューティングの会社であるSalesforce.comのテクノロジーを導入した。技術的な問題もなくスムーズに導入ができ、現在コミュニティーで一番ホットなトピックは「イノベーションとコラボレーション」で、しょっちゅう話し合われている。
このサイトを提供するにあたっては、CEOのマイケル・デルはコミュニティーの活用に大変乗り気であったが、他の役員がコミュニティーのリスクを考え、躊躇していた。しかし、このサイトを利用して「カスタマーと会社が製品及びサービスにおいてコラボレーションする」というメリットの方がリスクをはるかにうわまわるということで最終的には合意を得、社員からトップにいたる全社的な理解を得てからスタートすることができた。
このサイトを利用した成果として何よりも大きかったのが、Linuxラップトップの製品化につながったことである。それまでは、同社では、ラップトップの商品化には反対の姿勢を通していた。しかし、このサイトを通してラップトップを出すというアイデアが圧倒的に多いということを知り、実施した結果ヒット商品の一つとなったのである。
「何でも言える場」に知恵は集まる
2007年2月にIdeaStormをはじめたころは、「カスタマーからアイデアに対して投票してもらう」という考え方は珍しかった。成功の秘訣は、「参加者が言いたいことが言えるようにしたこと」である。開設当時は、カスタマーからは不平ばかりであまり前向きな意見はなかった。しかし同社では、あえてタッチせずにそのままにし、コミュニティー・メンバー達が「何でも言える」ようにしておいた。するとだんだんと参加意欲のあるメンバーが増え始め、いいアイデアが出始めた。ここから出たアイデアの多くはすでに製品化あるいはサービス向上につながっている。
ソーシャル・メディアの成果をどう測定?
同社においても財務的なメリットを図るのは難しいというのは他社と同様である。従来のような堅苦しい数字でROIを測ろうとはしていないが、利用率は測定しており、2006年ブログを提供し始めてから、「ソーシャルメディアの使い方のヒント」というfacebookの利用率は3万3千人のファンを超えたという。また、アイデアコンテストサイトでは、6000以上のアイデア(アイデアは「業務に生かされた」、「部分的に生かされた」、「評価中」、「評価済み」というようにカテゴリー化されている)が出され、75000以上のコメント、66万以上の投票があって、その結果として160のアイデアが業務に生かされている。
また、最初は気づかなかったが、このサイトを使っている間にカスタマーと結びつくのに大事な方法であることがわかってきた。それは、何が一番大事なのかが、全員が見えるように浮かび上がってくるからである。
コミュニティー運営側のチャレンジ
このようなコミュニティーを運営する側の問題としては、9600以上もあるアイデアをいかに社内で管理するかであった。多くの部署のある大企業にとっては大きな問題である。皆フルタイムで仕事をしているので、毎日レポートをしてもらい、意欲的に参加してもらうようにするのは、並大抵のことではなかった。「ちゃんときいていますよ」と何らかのフィードバックを出しきっちりと対応すること、それには、コミュニティーを管理する人が会社内に必要になってくる。デル社には約40人の社員が社内の部署の代表として「コミュニティーと会話」というグループに参加し、コミュニティーの「旗振り役」をしている。
2.共有とコラボレーション
ロッキード・マーチン社:組織がWeb2.0化するのはトップからは止められない
アイデアを共有しコンテンツを共同作成は日常業務
「せっかくすごいアイデアがあるんだけど、どうしたらみんなに知らせることができるんだろう?」
何年か前までは、このように思い悩んでいたエンジニアが多くいた。しかし、今は、ブログで全社に知らせることができるようになり、あるエンジニアが日常の仕事の中で「いいことを学んだよ!」とブログすると他のエンジニアがコメントするのは、同社では日常茶飯事の仕事光景となった。ブログからの気づきは社内Wikiに入るようになっており、皆で共有し、コンテンツは共同で作るというコンセプトがあたりまえになっている。
エンジニア、科学者の集合体の組織で、共有、コラボレーションがいかに大切なのかは誰もが認めることではあるが、組織が巨大化した結果、サイロ化現象が起こり、世界中に散らばっている組織の中にある知識がうまく共有できず、多くの重複した情報、業務プロセスの無駄が存在していた。高い機能のある大型LMSをいくつも早くから導入しているが、システム間の互換性等の問題があったりして、末端のエンドユーザー達が完全にその恩恵を得るには時間がかかっていた。このような既存のシステムに不満を感じていた社員から、ソーシャル・メディアの社内での使用についての多く要請があったが、宇宙防衛産業という機密性を要する仕事の性格上、なかなか導入に踏み切れなくていた。
しかし、企業としてグローバルな競争力をつけるには「共有とコラボレーションは欠かせない」というビジネス環境を考慮した経営トップの意向と、数年前から従来の研修のようなフォーマル・ラーニングを極力減らし、革新的なOJTで人材育成をしたいという教育トップの意向とも重なり、2007年よりソーシャル・メディア・プログラムのベータ版が動き始めた。
社内から社外へと広がったコラボレーション用ネットワーク
このベータ版は、プロジェクトチーム用のコラボレーションの場を作るのが目的で作られたUnityというプラットフォームである。このUnityは導入と同時に「待っていました」とばかりの勢いで膨れ上がり、3週間ごとに利用者が10%増という成長率であった。Unityを導入したことによって企業にもたらしたメリットはというと、「必要な人材と情報に迅速につながることによって結果としてユーザーの生産性が向上したこと」、「カスタマーが同社とコラボレーションをすることの関心を高めたこと」、「プロジェクトの提案書を書いたりする入札のためのプロセスをスピード化したこと」であった。
2009年には、ショーン・ダーレンが正式なソーシャル・メディア・プログラム・マネージャーとなり、Project Unityと呼ばれる社内用ソーシャルネットワーク(グーグル社のGoogle enterprise search appliance (GSA)、 Microsoft社の Windows Sharepoint Servicess (WSS)と NewsGator社の Enterprise Serverが使われている)となった。さらに同年7月には、iGoogle、 Facebook、 Twitterを一緒にしたようなソーシャル・メディアツールEureka Frameworkを追加し、これによって、社内(Chatterと言う社内用Twitterのようなもので経営トップ達がテスト中)だけではなく社外(取引先、政府関係機関)の情報についても、共有できるようにサイトに掲載し、社員達がうまく話し合ったりできるようになった。Eurekaはオープンソース・ソフトウェアを使っており、ユーザはコードを無料でもらってサイトを自分達用にカスタマ化したりすることができる。
このようにプロジェクトチーム用のコラボレーションの場として小さくスタートしたネットワークは、社内全体、そして社外のカスタマーとのコラボレーションの場と成長した。ダーレン氏によると、成功につながった秘訣は、社員にとっては「自分の仕事と別の余分な仕事」になっていないということである。プロジェクト用に今までやってきたこと(ドキュメント作成、スケジュール、アクションアイテム等)をメールを使ったりする代わりにコラボレーション用スペースに書き込むようにしただけである。このコラボレーション用スペースのプラットフォームは、ビジネス環境やユーザーのニーズに対応し常に変化している。
パワーは人脈があり、人と人を結びつけることができるかどうか
ソーシャル・ラーニングの導入は、企業文化と大きく関係している。ダーレン氏は「今までは、情報量のあることがパワーになるという考え方が強かったように思えますが、これからは、たくさんコネクションがあり、人と人を結びつけることができることがパワーであるという考え方が企業に必要だと思います。時間がかかるし、一夜でできないことですが。。。」と、競争力について自分の考え方をまとめていた。
今まで、ともかく外からの侵入者をいっさいシャットアウトで知られていた同社が、オープン性を基本にしたソーシャル・メディアを導入しGoogle社のように組織をWeb2.0化しようとしている姿勢は、教育業界にも大きなインパクトを与えたことは確かである。
インテル社:ライブな社内用百科事典 Intelpediaを共同作成
草の根的に成長
2007年、上級製品サポートエンジニアの一人が「Wikipediaのようなものが社内にあればどんなにいいだろうか」と提案し、オープンソースのソフトウェアを使ってやり始めた。するとそれを見た他の社員も賛同して活用しはじめた。これが、社内用インテルペディアの誕生である。開設と同時に社外の人達までが、インテルの歴史をはじめとしてプロジェクト更新関連にいたるまで、あらゆるトピックについて掲載しはじめた。インテル社の社員間でもファンは増加し、現在、5000人以上の現役の書き手、2万ページが以上が掲載されており、閲覧ページ数は1日に20万ページ以上で、社内で2番目に閲覧者数が多いサイト(1番目は、インテル社のイントラネットのホームページ)になった。
興味深いのは、この動きは完全に草の根的であったことである。企業側から、サイトを作り社員が使うようにとの支持もなければ、インテルペディア使用上の長々とした規則もなかった。唯一の規則としては「今までの企業のポリシーに従うこと(秘密情報、競合社一般に知らせてはいけない知的資産を守ること)」、「掲載する内容は少なくとも他の社員一人に役立つものであること」の2つだけであった。
会社が受け入れられる情報損失量とは?
インテルペディアはこのように高い利用率という成功を収めたが、この成功を通して今まで考えても見なかった質問が社内で出てきた。
これらの質問に対して話し合っている中で、「専門家」に対する定義が大きく変わった。特に4番の質問に対して、「どこにも存在していなかった」が作らなければならないものであったことが判明したことは、「今までどれだけ必要な情報を損失していたか」に気づくいいきっかけであった。インテルペディアというシンプルなプラットフォームを提供するだけで、インテル社はたった2年弱で、2万ものコンテンツページを社内で共有できるようになったのである。それも、今まで、社員は共有したいと思っていたが、できなかったことが、できるようになったのである。
3.最後に
ここでご紹介したソーシャル・メディアを利用した企業事例が必ずしも読者の会社のビジネスにあてはまるわけではないので、これをこのままお勧めすることはできない。しかし、ここで言えることは、ソーシャル・メディアをうまく生かしたソーシャル・ラーニングは、企業が10年後生き残っているのに必要なラーニングにつながっているということである。なぜなら、ソーシャル・ラーニングは組織を「グーグル化」し、以下のことを企業にもたらすからである。
前回はTwitterに焦点をあて、サウスウェスト航空、デルにおける取り組み事例をご紹介した。今回はより広くソーシャル・ラーニングに取り組んでいる企業の事例と、そこから見えてくるメリットや課題について考察する。
1.イノベーション
企業の将来的成長にはイノベーションは欠かせないと分かっていても、不況のときにイノベーションにつながるための基礎研究に時間と投資をすることは難しい。大手電力会社のPacific Gas & Electric はWeb上にコンテストの場を提供し、社外から製品アイデアを募った結果、イノベーションを創出し乗り切ってきた企業の一つである。今ではPG&E社のイノベーションの50%以上は社外からだという。PG&E社のように、社内と社外を結びつけた「ソーシャル・ラーニング」を通してイノベーションを創出している企業は多い。
デル社:社内からは生まれなかったヒット商品
社外からのアイデアが商品化
コンピューター会社デルのIdeaStormは、カスタマーや一般から製品アイデアを出してもらうというコミュニティー・サイトである。カスタマーも社員も使いやすいようにということを第一として、クラウドコンピューティングの会社であるSalesforce.comのテクノロジーを導入した。技術的な問題もなくスムーズに導入ができ、現在コミュニティーで一番ホットなトピックは「イノベーションとコラボレーション」で、しょっちゅう話し合われている。
このサイトを提供するにあたっては、CEOのマイケル・デルはコミュニティーの活用に大変乗り気であったが、他の役員がコミュニティーのリスクを考え、躊躇していた。しかし、このサイトを利用して「カスタマーと会社が製品及びサービスにおいてコラボレーションする」というメリットの方がリスクをはるかにうわまわるということで最終的には合意を得、社員からトップにいたる全社的な理解を得てからスタートすることができた。
このサイトを利用した成果として何よりも大きかったのが、Linuxラップトップの製品化につながったことである。それまでは、同社では、ラップトップの商品化には反対の姿勢を通していた。しかし、このサイトを通してラップトップを出すというアイデアが圧倒的に多いということを知り、実施した結果ヒット商品の一つとなったのである。
「何でも言える場」に知恵は集まる
2007年2月にIdeaStormをはじめたころは、「カスタマーからアイデアに対して投票してもらう」という考え方は珍しかった。成功の秘訣は、「参加者が言いたいことが言えるようにしたこと」である。開設当時は、カスタマーからは不平ばかりであまり前向きな意見はなかった。しかし同社では、あえてタッチせずにそのままにし、コミュニティー・メンバー達が「何でも言える」ようにしておいた。するとだんだんと参加意欲のあるメンバーが増え始め、いいアイデアが出始めた。ここから出たアイデアの多くはすでに製品化あるいはサービス向上につながっている。
ソーシャル・メディアの成果をどう測定?
同社においても財務的なメリットを図るのは難しいというのは他社と同様である。従来のような堅苦しい数字でROIを測ろうとはしていないが、利用率は測定しており、2006年ブログを提供し始めてから、「ソーシャルメディアの使い方のヒント」というfacebookの利用率は3万3千人のファンを超えたという。また、アイデアコンテストサイトでは、6000以上のアイデア(アイデアは「業務に生かされた」、「部分的に生かされた」、「評価中」、「評価済み」というようにカテゴリー化されている)が出され、75000以上のコメント、66万以上の投票があって、その結果として160のアイデアが業務に生かされている。
また、最初は気づかなかったが、このサイトを使っている間にカスタマーと結びつくのに大事な方法であることがわかってきた。それは、何が一番大事なのかが、全員が見えるように浮かび上がってくるからである。
コミュニティー運営側のチャレンジ
このようなコミュニティーを運営する側の問題としては、9600以上もあるアイデアをいかに社内で管理するかであった。多くの部署のある大企業にとっては大きな問題である。皆フルタイムで仕事をしているので、毎日レポートをしてもらい、意欲的に参加してもらうようにするのは、並大抵のことではなかった。「ちゃんときいていますよ」と何らかのフィードバックを出しきっちりと対応すること、それには、コミュニティーを管理する人が会社内に必要になってくる。デル社には約40人の社員が社内の部署の代表として「コミュニティーと会話」というグループに参加し、コミュニティーの「旗振り役」をしている。
2.共有とコラボレーション
ロッキード・マーチン社:組織がWeb2.0化するのはトップからは止められない
アイデアを共有しコンテンツを共同作成は日常業務
「せっかくすごいアイデアがあるんだけど、どうしたらみんなに知らせることができるんだろう?」
何年か前までは、このように思い悩んでいたエンジニアが多くいた。しかし、今は、ブログで全社に知らせることができるようになり、あるエンジニアが日常の仕事の中で「いいことを学んだよ!」とブログすると他のエンジニアがコメントするのは、同社では日常茶飯事の仕事光景となった。ブログからの気づきは社内Wikiに入るようになっており、皆で共有し、コンテンツは共同で作るというコンセプトがあたりまえになっている。
エンジニア、科学者の集合体の組織で、共有、コラボレーションがいかに大切なのかは誰もが認めることではあるが、組織が巨大化した結果、サイロ化現象が起こり、世界中に散らばっている組織の中にある知識がうまく共有できず、多くの重複した情報、業務プロセスの無駄が存在していた。高い機能のある大型LMSをいくつも早くから導入しているが、システム間の互換性等の問題があったりして、末端のエンドユーザー達が完全にその恩恵を得るには時間がかかっていた。このような既存のシステムに不満を感じていた社員から、ソーシャル・メディアの社内での使用についての多く要請があったが、宇宙防衛産業という機密性を要する仕事の性格上、なかなか導入に踏み切れなくていた。
しかし、企業としてグローバルな競争力をつけるには「共有とコラボレーションは欠かせない」というビジネス環境を考慮した経営トップの意向と、数年前から従来の研修のようなフォーマル・ラーニングを極力減らし、革新的なOJTで人材育成をしたいという教育トップの意向とも重なり、2007年よりソーシャル・メディア・プログラムのベータ版が動き始めた。
社内から社外へと広がったコラボレーション用ネットワーク
このベータ版は、プロジェクトチーム用のコラボレーションの場を作るのが目的で作られたUnityというプラットフォームである。このUnityは導入と同時に「待っていました」とばかりの勢いで膨れ上がり、3週間ごとに利用者が10%増という成長率であった。Unityを導入したことによって企業にもたらしたメリットはというと、「必要な人材と情報に迅速につながることによって結果としてユーザーの生産性が向上したこと」、「カスタマーが同社とコラボレーションをすることの関心を高めたこと」、「プロジェクトの提案書を書いたりする入札のためのプロセスをスピード化したこと」であった。
2009年には、ショーン・ダーレンが正式なソーシャル・メディア・プログラム・マネージャーとなり、Project Unityと呼ばれる社内用ソーシャルネットワーク(グーグル社のGoogle enterprise search appliance (GSA)、 Microsoft社の Windows Sharepoint Servicess (WSS)と NewsGator社の Enterprise Serverが使われている)となった。さらに同年7月には、iGoogle、 Facebook、 Twitterを一緒にしたようなソーシャル・メディアツールEureka Frameworkを追加し、これによって、社内(Chatterと言う社内用Twitterのようなもので経営トップ達がテスト中)だけではなく社外(取引先、政府関係機関)の情報についても、共有できるようにサイトに掲載し、社員達がうまく話し合ったりできるようになった。Eurekaはオープンソース・ソフトウェアを使っており、ユーザはコードを無料でもらってサイトを自分達用にカスタマ化したりすることができる。
このようにプロジェクトチーム用のコラボレーションの場として小さくスタートしたネットワークは、社内全体、そして社外のカスタマーとのコラボレーションの場と成長した。ダーレン氏によると、成功につながった秘訣は、社員にとっては「自分の仕事と別の余分な仕事」になっていないということである。プロジェクト用に今までやってきたこと(ドキュメント作成、スケジュール、アクションアイテム等)をメールを使ったりする代わりにコラボレーション用スペースに書き込むようにしただけである。このコラボレーション用スペースのプラットフォームは、ビジネス環境やユーザーのニーズに対応し常に変化している。
パワーは人脈があり、人と人を結びつけることができるかどうか
ソーシャル・ラーニングの導入は、企業文化と大きく関係している。ダーレン氏は「今までは、情報量のあることがパワーになるという考え方が強かったように思えますが、これからは、たくさんコネクションがあり、人と人を結びつけることができることがパワーであるという考え方が企業に必要だと思います。時間がかかるし、一夜でできないことですが。。。」と、競争力について自分の考え方をまとめていた。
今まで、ともかく外からの侵入者をいっさいシャットアウトで知られていた同社が、オープン性を基本にしたソーシャル・メディアを導入しGoogle社のように組織をWeb2.0化しようとしている姿勢は、教育業界にも大きなインパクトを与えたことは確かである。
インテル社:ライブな社内用百科事典 Intelpediaを共同作成
草の根的に成長
2007年、上級製品サポートエンジニアの一人が「Wikipediaのようなものが社内にあればどんなにいいだろうか」と提案し、オープンソースのソフトウェアを使ってやり始めた。するとそれを見た他の社員も賛同して活用しはじめた。これが、社内用インテルペディアの誕生である。開設と同時に社外の人達までが、インテルの歴史をはじめとしてプロジェクト更新関連にいたるまで、あらゆるトピックについて掲載しはじめた。インテル社の社員間でもファンは増加し、現在、5000人以上の現役の書き手、2万ページが以上が掲載されており、閲覧ページ数は1日に20万ページ以上で、社内で2番目に閲覧者数が多いサイト(1番目は、インテル社のイントラネットのホームページ)になった。
興味深いのは、この動きは完全に草の根的であったことである。企業側から、サイトを作り社員が使うようにとの支持もなければ、インテルペディア使用上の長々とした規則もなかった。唯一の規則としては「今までの企業のポリシーに従うこと(秘密情報、競合社一般に知らせてはいけない知的資産を守ること)」、「掲載する内容は少なくとも他の社員一人に役立つものであること」の2つだけであった。
会社が受け入れられる情報損失量とは?
インテルペディアはこのように高い利用率という成功を収めたが、この成功を通して今まで考えても見なかった質問が社内で出てきた。
- 2万ページのうち専門知識のある人すなわち「専門家」と呼ばれている人が作成したのはどれだけ?
- 現役の書き手5000人のうち何人が「専門家」として社内で認められているか?
- これらの掲載内容は組織にとって付加価値となっているか?誰が関心があるのか?
- 2万の書き込みのうちどれだけが、企業組織の中ですでに存在していたものか?
これらの質問に対して話し合っている中で、「専門家」に対する定義が大きく変わった。特に4番の質問に対して、「どこにも存在していなかった」が作らなければならないものであったことが判明したことは、「今までどれだけ必要な情報を損失していたか」に気づくいいきっかけであった。インテルペディアというシンプルなプラットフォームを提供するだけで、インテル社はたった2年弱で、2万ものコンテンツページを社内で共有できるようになったのである。それも、今まで、社員は共有したいと思っていたが、できなかったことが、できるようになったのである。
3.最後に
ここでご紹介したソーシャル・メディアを利用した企業事例が必ずしも読者の会社のビジネスにあてはまるわけではないので、これをこのままお勧めすることはできない。しかし、ここで言えることは、ソーシャル・メディアをうまく生かしたソーシャル・ラーニングは、企業が10年後生き残っているのに必要なラーニングにつながっているということである。なぜなら、ソーシャル・ラーニングは組織を「グーグル化」し、以下のことを企業にもたらすからである。
- イノベーションを継続的に生む
- コラボレーションと共有を通して学ぶ
- 組織を透明化しフラット化する
- 自律性のある人材育成に役立つ
- 社員とマネージャーとの信頼関係を強化する
- 社員のコンピテンシーを身に付けるスピードが速くなる
- 顧客関係を強化する
- 生産性を向上する
- 変化とスピードに対応したグローバルな競争力が増す
- 離職率が低くなる
- ラーニングへの投資コストが低くて済む
« 第29回 上流から見たeラーニング 11 ビジネスの成長と社員の成長につながる「ソーシャル・ラーニング」前篇 | 第31回 上流から見たeラーニング 13 「歴史ある大手企業がインフォーマル/ ソーシャル・ラーニングにシフトしている」 前編 »
- HOME
- デジタルラーニング関連情報
- アーカイブ
- ◆連載「海外のeラーニング事情」(2003年~2014年)
- 第30回 上流から見たeラーニング 12 ビジネスの成長と社員の成長につながる「ソーシャル・ラーニング」後編
- SCORM関連情報
- SCORMとは
- SCORM技術者一覧
- SCORM適合LMS
- SCORM適合コンテンツ
- SCORM関連各種
ダウンロード
- デジタルラーニング
- デジタルラーニング・
ショーケース - eラーニング・ショーケース
- 調査報告
- リンク
- 用語集
- アーカイブ
DLCメールニュースの配信をご希望の方へ
eラーニング、デジタルラーニングに関するイベント
セミナー、技術情報、開講案内などのニュース配信は
下記よりご登録をお願いいたします。
「DLCメールニュース」配信登録フォーム